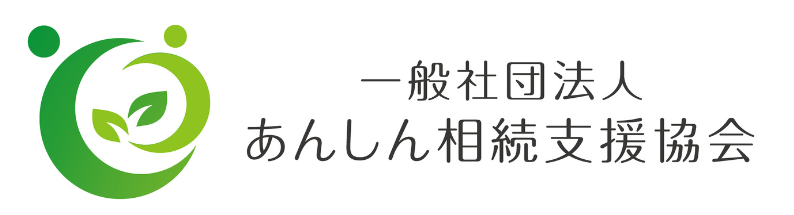【はじめに】
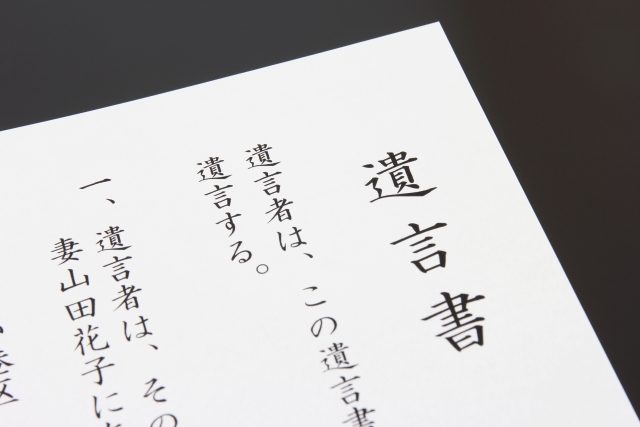
「遺言書を書いておけば安心」と思っていませんか?
実は、書き方を間違えると「無効」になったり最悪、家族に争いを残してしまうことがあります。せっかくの想いが届かないのは避けたいものです。
今回は、「書いてはいけない悪い遺言書」とは何か? 山梨で終活を考える皆さまに分かりやすく解説します。
※本記事は令和7年8月時点の情報に基づいております。
【なぜ悪い遺言書がトラブルを招くのか?】
なぜ悪い遺言書がトラブルを招くのか?
遺言書は財産分けや想いを伝える大切な書類ですが、法律(民法968条)で定められたルールを守らないと無効になります。さらに、あいまいな表現や不公平な内容は、相続争いの火種になりうることもあります。
「書いたけれど相続で使えなかった」、「内容があいまいでそれにより兄弟間で争いに発展した」ということも少なくありません。
書いてはいけない!悪い遺言書の特徴7選
1. 法的要件を守っていない
・日付がない、あるいは吉日などと書かれていて書いた日を特定できない場合
・署名や押印がない
・代筆してしまった(自筆証書遺言の場合)
・書き損じた箇所の訂正方法が法に則っていない
→自筆証書遺言は特に要注意!
・同じ紙に複数人が遺言をする(共同遺言)も無効になります。
2. あいまいな表現

「できるだけ平等に分けてください」、「家は子供に平等に残します」、「財産を託す」、「財産を任せる」などの曖昧な言葉は、解釈の違いで争いに発展します。
「だれに」、「どの財産を」相続させるというように特定できる内容にする必要があります。
例えば「財産を任せる」だと財産をどうするべきかがあいまいになってしまいますしどの財産なのかが特定されていません。
一般的に、相続人に対しては「相続させる」と記載し、相続人以外の人に財産を残す場合は「遺贈する」と記載します。
また、財産は預貯金の場合は金融機関名や口座番号、不動産の場合は地番や家屋番号などきちんと特定できる情報の記載が必要です。
3. 不公平すぎる内容

特定の相続人を極端に優遇したり、全く財産を与えないと遺留分侵害でトラブルになり得ます。
遺留分とは相続人が請求することのできる取り分ともいえるもので、金銭での精算となります。
特に、財産が不動産しかない場合で、その不動産を長男に相続させる内容の遺言にした場合、長男は他の相続人に支払う遺留分額や相続税の納税資金を自ら捻出しなければいけない事態になり、大きな負担を抱えてしまいます。
4. (遺言書として)意味のないの遺言書
「仲良くしてください」「いままでありがとう」などの最後の手紙のような遺言書は法的効力がない内容のみになりますので遺言書としては意味がありません。
あくまで財産を誰に相続させるか等の遺言書本文を書いたうえで、付言事項としてそういった内容を書くことは問題ありません。
5. 専門家のチェックを受けていない

形式面の間違いなどに気が付かず、せっかくの遺言が無効になる可能性があります。
特に自筆証書遺言の場合で専門家の関与がない場合は自分だけで完結してしまうこともあります。
いざ亡くなって遺言書が発見されても「使えない遺言書だった」、「内容が争いを引き起こすような内容だった」など最悪のパターンのなることも
6. 遺言能力が無い場合
認知症などで判断能力がない状態でされた遺言は遺言能力が無い状態で書かれたものとなり、無効になる可能性があります。
7.その他
遺言書を自宅で保管している場合で、湿気の多いところなど保管してしまった場合など、保管状態が悪くて劣化し、いざ開封したら読めなくなっていたり、不要な書類と一緒に間違って廃棄してしまったり、様々なリスクがあります。
自筆証書遺言の場合、法務局の「自筆証書遺言保管制度」の利用を検討するとこういったリスクを防ぐことが出来ます。
【どうすれば「良い遺言書」になるのか?】

・法律に沿った形式で作成する
・相続人全員が納得できる内容を意識
・公正証書遺言の活用で確実性を高める
・専門家(行政書士・司法書士・弁護士)に相談する
【まとめ】
悪い遺言書は、家族の幸せを守るどころか、争いを生む原因になります。
「自分の想いを正しく伝える遺言書」を作ることが大切です。
遺言書を書くことは良いことですが、それは正しい遺言書に限ります。
悪い遺言書を書いてしまい、「これじゃ書かない方がよかった」なんて結果になることも
山梨で遺言書や終活のご相談は、私たち「あんしん相続支援協会」へお気軽にどうぞ!
お問い合わせは下記リンク
または電話 0120-962-974 までお願いいたします。