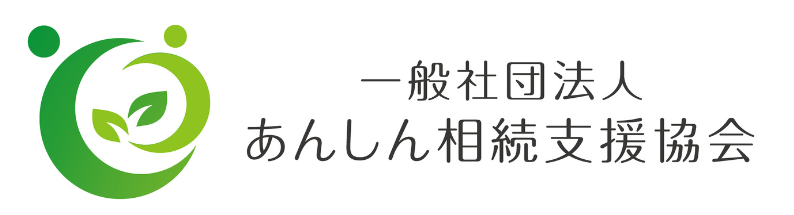1. 任意後見制度とは?

「任意後見制度」は、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に自分の財産管理や身上監護(生活・医療・介護の手続きなど)を任せることができる制度です。
認知症や病気などで判断能力が衰えた場合でも、任意後見の受任者(契約書で定めた内容を実行する人)が本人すなわち委任者が望む内容に基づいて財産管理や契約手続きができるため、自分の意思を尊重した生活を送ることが可能になります。
任意後見契約の主な特徴:
- 判断能力があるうちに自信が望む人物と契約を結びます。(例外はありますが自身が望んだ人と任意後見契約を結ぶことが出来ます。)
- どのような支援を任せるかを自分で決められます。
- 公証役場で契約を公正証書にする必要があります。
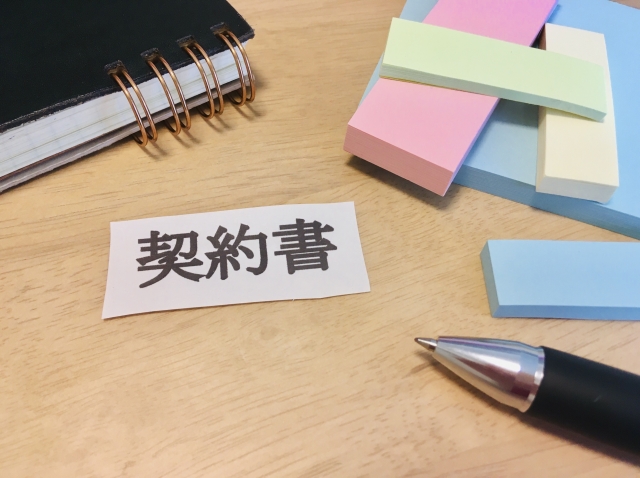
2. 任意後見と法定後見の違い
任意後見とよく混同されるのが「法定後見」です。それぞれの違いを以下にまとめます。
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 判断能力があるうちに契約し、判断能力が低下したら開始(備える型) | 判断能力が低下した後に家庭裁判所に申し立てて開始(事が起きてから型) |
| 契約の内容 | 本人が自由に決められる | 家庭裁判所が定める |
| 監督機関 | 任意後見監督人(家庭裁判所が選任) | 後見監督人(家庭裁判所が選任) |
| 対応範囲 | 財産管理、身上監護、契約手続きなど | 財産管理、身上監護が中心(契約手続きは制限される場合がある) |
| 契約手続き | 公証役場で公正証書を作成 | 家庭裁判所への申し立てが必要 |
👉 任意後見制度は、本人が意思決定できる間に自分で内容を決めておけるため、自分の希望を尊重した生活を維持できるのが大きなメリットです。

3. 任意後見制度を利用するメリット
✅ 自分の意思を反映できる
任意後見では、誰にどのような支援を頼むかを自分で決められます。信頼できる家族や専門家に依頼できるため、安心感があります。法定後見の場合は自身で決めることはできません。
✅ 財産管理がスムーズになる
信頼できる人を任意後見人にした場合、将来的に認知症や病気で判断能力が低下しても、任意後見人が適切に財産管理を行えるため、トラブルを未然に防げます。(反対に、不適切な人物を任意後見人にした場合は適切に義務を履行してくれなかったり、財産の使い込みをしてしまうなど、トラブルの原因になる可能性もあります。)
✅ 身上監護も可能
生活支援や医療・介護手続きなど、身上監護を任せることもできるため、生活の安心感が高まります。(これも適切な人物を任意後見人にした場合のメリットです。)
4. 山梨県で任意後見の相談ができる場所
任意後見契約は将来の生活設計に関わる重要な契約です。専門家に相談しながら慎重に進めることが大切です。山梨県で相談できる主な窓口は以下の通りです。

🏢 県内の士業団体(山梨県行政書士会など)
- 山梨県行政書士会では市役所などと連携して行政書士による無料相談会を開催しています。無料相談会の際に任意後見についての相談も可能です。(ただし、相談員を務める行政書士の専門性によっては相談できない場合もあります。)
🏢 山梨県の社会福祉協議会
- 成年後見制度に関する相談が可能です。
(例) - 甲府市社会福祉協議会
- 山梨市社会福祉協議会
🏢 地域包括支援センター
- 成年後見制度に関する基礎的な相談が可能です。
- 地域包括支援センターの場所や連絡先は、各市町村の役所やホームページで確認できます。
🏢 民間の終活サービス事業者(NPO法人や一般社団法人など)
- 民間ですので相談に料金がかかる場合もありますが初回相談が無料の団体もあります。相談をする団体に任意後見に関する知識を持った専門職(弁護士、行政書士など)が所属あるいは提携していることが望ましいです。また、終活サービスを包括的に行っている団体の場合、任意後見契約以外にも遺言書や相続、亡くなった後の手続きなどの相談もワンストップで可能です。
「一般社団法人あんしん相続支援協会」では、お客様のライフプランを作成し、そのライフプランに沿って、お客様がご希望の終活サービスを提供いたします。もちろん初回相談は無料です。 - あんしん相続支援協会 – あなたに寄り添う 伴走者
5. 任意後見契約の流れ
- 契約内容の検討
どのような支援を任せるかを決めます。財産管理や生活支援、医療・介護の手続きなど、具体的な内容を決めます。 - 任意後見人の選定
信頼できる家族や専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)を選びます。 - 公証役場で契約
公証役場で任意後見契約を結びます。契約書は公正証書として作成します。
本人の意思と判断能力をしっかりと確認して、契約の内容がきちんと法律に従ったものであることを法的知識と経験を有する公証人が作成する公正証書にします。 - 任意後見監督人の選任
判断能力が低下した際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。 - 契約の実行
契約内容に従い、任意後見人が支援を開始します。
6. まとめ:任意後見契約で将来への備えを

山梨県でも、認知症や病気による判断能力の低下に備えて、任意後見契約を結ぶ人が増えています。
自分の意思を尊重した生活を送るために、任意後見制度の活用を検討してみましょう。
💡 任意後見契約の相談、その他相続、終活の相談は当協会でも受け付けています。
「老後が心配」、「子供に迷惑をかけたくない」、「親の相続、終活はどうすれば?」、「遺言書、相続について知りたい」、「理想のエンディングを作りたい」そういったお悩みやご希望をお持ちの方へ、将来への備えを始めてみませんか?
#山梨県 #任意後見 #成年後見 #法定後見 #遺言書 #あんしん #相続 #終活 #行政書士